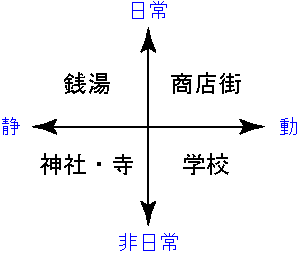
ぼくは東京に住むようになってこのかた、まだ風呂付きの部屋というのに住んだことがない。それでだいたいは銭湯のお世話になっている。東京という町はそういう風呂なしの民に対してとてもやさしい町である。だいだいどこへ行っても銭湯がある。もちろん最近になって新しく開かれた住宅地などにはないかもしれないが、ある程度の歴史をもったところならばかならず一軒は銭湯がある。そういった意味では、銭湯の存在は東京の町の歴史を感じさせてくれる。
ぼくのイメージする「町」とはこんなところである。まず商店街がある。そこは車なんかは通らない。人々が犬猫が行き交っている。それから神社かお寺がある。そうした宗教的な象徴が求心力となって町ができあがってもよいのだけれど、かならずしもそういった門前町でなくてもよい。それから町のはずれに学校がある。町を見下ろす高台なんかにあるとなおよいだろう。そうして銭湯が町の真ん中にある。商店街、神社もしくはお寺、学校、銭湯。これらがぼくのイメージする町を形成する必須の要素である。
これらはすべて人の集まる場所である。たとえば神社とかお寺とかいうところは、そうそう頻繁に訪れるところではないかもしれないが、年に一度のお祭りだとか、お葬式だとか、まあいろいろあるのだろうけれども、ともかく人の集まるところである。それは人々の精神的なよりどころである。それから学校はなにも子供だけが集まるところではなくて、運動会だとか、選挙だとか、ごくたまになにかのイベントを行うにはとても便利なところである。それから商店街と銭湯とは、日常的に人々が集うところである。商店街はビジネスの中心であり昼の営みの中心であるが、一方の銭湯は仕事が終わったあとの集いの場である。
いま仮にこれら四つの場所を「日常と非日常」および「動と静」という二つの軸でもって、知ったようなふりをして分類してみるとすれば下の絵のようになるだろうか。
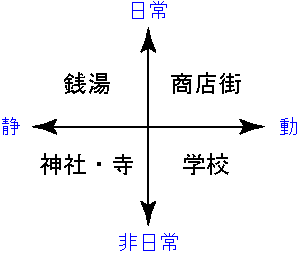
まず学校と神社・お寺とを考えてみよう。これらはともに非日常的な場である。もちろん子供にとっては学校は日常であったり、また坊さんにはお寺が日常であったりするだろうが、まあ一般的な観点ではともに非日常の場であると思う。学校というのは教育の場であり、みんな一度はそこに通ったはずのところである。学校に対して、人は懐かしさを覚える、また人は尊敬の念を覚える。学校の先生はだいたいにおいて尊敬されるものである。校長先生などといったらその町の知性の象徴的存在でさえある。
神社やお寺というのも学校と似た性格をもっている。ここは人々のこころのよりどころである。学校が知の象徴だとすれば、こちらは精神世界の象徴である。これら二つを動と静というふうに区切るのはあまり適当ではないかもしれない。ただまあ学校は教育や研究の場であり、なにか生産的なイメージをもっているのに対して、神社・お寺というのはひっそりと人々の背後で見守ってくれている感じがする。いずれにせよ、この二つの存在は、毎日毎日その世話になるというものではないが、町の人々の精神的安定を支えてくれているといえる。
次に商店街(もしくは仕事場といったほうが適当かもしれない)と銭湯とを比べてみよう。これらは明らかに人々が日常的に集うところである。商店街とは労働の場であり、それぞれが生活の糧をそこで得ている。一方の銭湯とはそうした労働が終わったあとに休息する場である。そこで一日の汗を洗い流すのである。したがってこれら二つを動と静とするのはまあそれほど見当はずれではないと思う。
やっぱり上の絵のように四つの場所を「日常・非日常」、「動・静」のキーワードでくくってしまったのには無理があったかもしれない。それでもああいうふうにならべてみるとおもしろいことも見えてきたりするもので、たとえば銭湯と神社・お寺とがともに癒しの場である、などと言えたりする。そうすると「日常と非日常」というくくり方よりは、むしろ「現実と理想」などとしたほうがよかったのかもしれない。垢を落とすのは日々しかたなくする現実的な作業であるが、こころの垢を落とすなどというのは理想的な物言いである。
さて本題の「銭湯を賛す」ことに戻ろう。日常世界、あるいは現実世界において、人々が仕事を離れてともに集い、休息をもとめるところ、それが銭湯である。人が生活の糧を得る手段はみなばらばらである。労働の場は人それぞれに違うものである。ところがそうした労働が終わったあと、人々が集う場があるということは実に意義深いものであると思う。そこではお互いが生きていることを確認し合うことができる。さまざまな情報を交換し合うことができる。昼の世界では顔を合わすこともないけれども、風呂にはいるという行為を介して、お互いに接点をもつことができる。そのような貴重な場を銭湯は提供してくれるのである。
だからそういう意味ではなにも銭湯だけが偉いわけではなく、たとえば夜な夜な人々が集う酒場とか飯屋なんかもそうした機能をあわせもっている。けれども銭湯というところはコミュニケーションの場としてもっとも適したところなのである。まずみんな裸になるというところがすばらしい。お金をもっていようがなんだろうがみんな裸になるわけである。これほどさっぱりしたところはない。
それから老若男女がみんな集うというところがすばらしい。もちろん男湯と女湯とは分かれているのであるが、それにしてもあらゆる世代の人々がともに同じ時を同じ場で過ごすことによって、なにか一体感みたいなものを感じることができる。そうした瞬間が毎日訪れるのだから、それは実に有意義であるといわねばならない。
このようなことすべてを含めて銭湯というものを考えたとき、ぼくがイメージする「町」の構成要素のひとつとして銭湯をとりあげたことは、なにかしら理由のあることであると認めてもらえるだろうか。しかし昨今の社会事情から、銭湯は衰退の一途をたどっているという。みんな風呂付きの家に住むので、銭湯の存在意義がなくなったという。これはさびしいことである。
そんなことをいうと、たとえば学校の価値もまた低下しているのかもしれない。学級崩壊などという言葉を聞く。先生に対する尊敬の念みたいなものもなくなってしまったのかもしれない。それから商店街もまた、大規模スーパーの進出やコンビニエンスストアの氾濫で衰退しているという。
ぼくがイメージした町とは、伝統的な意味での町であって、現代的な観点からすれば古臭いものであるかもしれない。しかしそうはいっても、少なくとも過去のある時代において、銭湯は町を構成する要素のひとつとして、ほかにはないすばらしい役割を果たしていた。それをやすやすとなくしてしまうのは惜しい気がする。
銭湯は社会の窓である。銭湯文化を残そう。それをただの文化財的な見方で残そうというのではなく、積極的に社会の中でその長所を活用する形で残そう。
「1010」という小冊子がある。「せんとう」と読む。これは東京都の銭湯組合が発行している広報誌で、銭湯に行くとおいてある。これを読むとなるほど銭湯にこだわりをもつ人が多いのが分かる。とくに読者のお便りなどをみると銭湯好きの人をたくさん見出すことができる。
銭湯のよさは銭湯に行ってみないとわからない。なるだけ銭湯の真価を解する人が増えることを望む。
1999 年 9 月 5 日